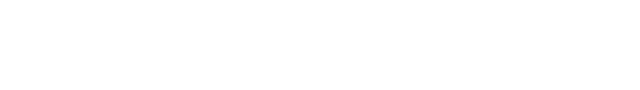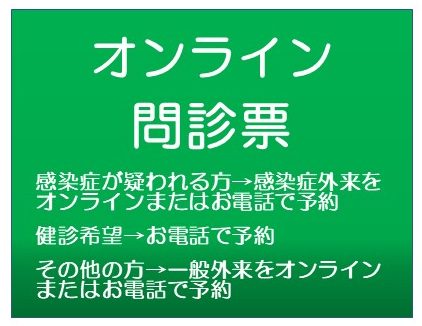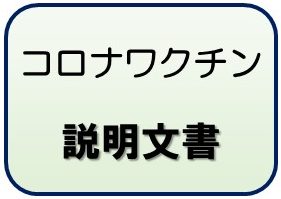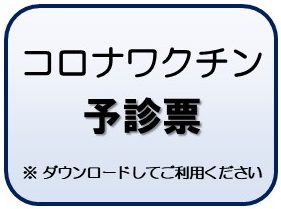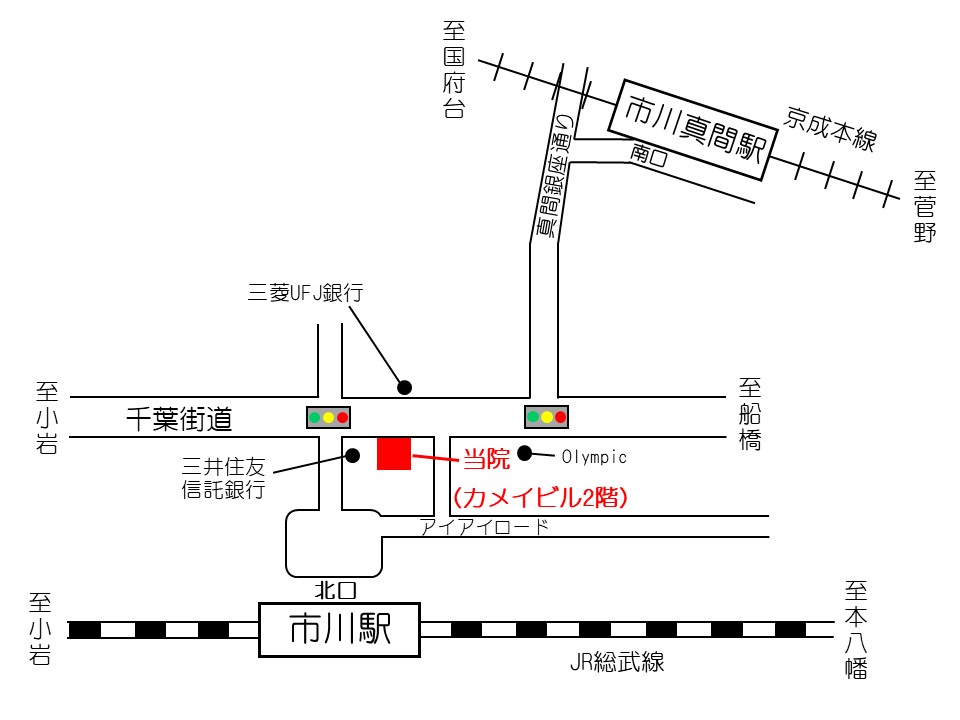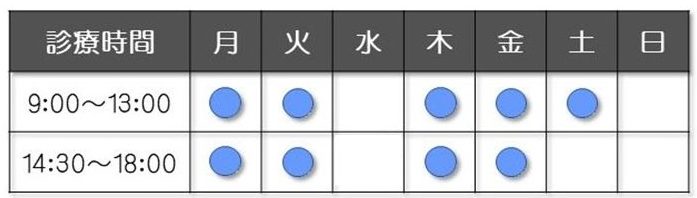橋本病と妊娠
1.橋本病とは
2.不妊と橋本病
5.産後のケア
橋本病は、自己免疫疾患の一つであり、甲状腺の機能が低下する病気です。「慢性甲状腺炎」とも呼ばれ、甲状腺が炎症を引き起こすことで甲状腺ホルモンの分泌が低下する「甲状腺機能低下症」を引き起こします。中高年の人に多く見られ、特に女性に多いです。甲状腺ホルモンは代謝やエネルギー消費を調整するため、甲状腺機能低下症になると、疲れやすさ、体重増加、冷え性、便秘などの症状が現れます。
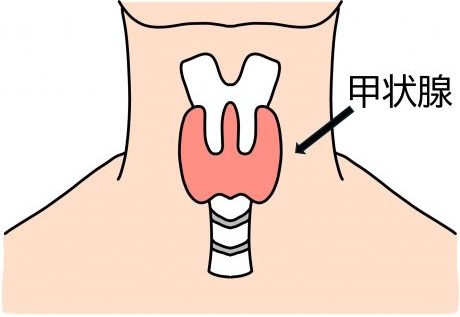
橋本病が原因で不妊症になることがあり、橋本病は不妊の原因となる因子の中で、以下に示すような2つの因子(排卵因子、男性因子)と関係しています。

橋本病による甲状腺ホルモン分泌の不足は、女性の場合、性ホルモンの分泌に影響を及ぼし、卵胞の発育が低下することで排卵しにくくなる原因となります。また、男性の場合は、奇形精子症や精子の運動能低下、精液量や射精量の減少を引き起こします。
1)知能や運動能力への影響
妊娠初期において甲状腺ホルモンは胎児の発達に不可欠です。橋本病によって母体から送られる甲状腺ホルモンの不足が胎児の知能や運動能力の発達に悪影響を及ぼすリスクがあります。

2)流産や早産のリスク増加
甲状腺ホルモンの不足が流産や早産につながることがあります。
甲状腺ホルモンの不足を甲状腺刺激ホルモン(TSH)値によって確認します。TSH値と妊娠段階に応じてチラーヂンS®(合成T4製剤)の服用をします。米国甲状腺学会ガイドライン 2017では、TSH値は妊娠初期で2.5 μIU/L未満、中期および後期で3.0 μIU/L未満に抑えることが推奨されており、適切な範囲を維持するために血液検査を行い、検査結果に応じて薬の量を調整します。

産後、橋本病の方は甲状腺ホルモンの必要量が妊娠前の状態に戻るため、多くの場合、チラーヂンS®の量を減らしたり、中止したりします。薬の服用が胎児に影響することはなく、授乳も問題なく行えます。産後も甲状腺機能を定期的に確認し、必要に応じて薬を再開・調整しながら適切なケアを続けることが重要です。